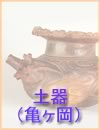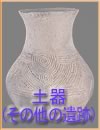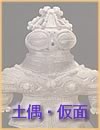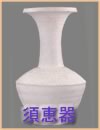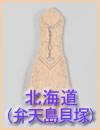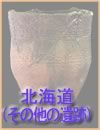| |
|
 |
1.
旧石器時代・石器
初期には,礫(レキ)を打ち欠いて作るチョッパ‐(片刃礫器),チョッピング・ツール(両刃礫器)やハンドアックス(手斧)が作られ,やがて剥片を加工したナイフ,彫刻刀,スクレイパー(削り具)や尖頭器(せんとうき)が作られるようになりました。最後期には,替え刃として使った細長い剥片(細石刃(さいせきじん))を剥ぐ技術が広がりました。
ここでは,大分県早水台(そうずだい)遺跡,岩戸(いわと)遺跡,栃木県星野(ほしの)遺跡,磯山(いそやま)遺跡などから出土した石器資料をご覧いただけます。
左写真は,早水台遺跡出土のチョッピング・ツールです。(撮影:芹沢長介)
|
| |
|
|
|
旧
石
器
時
代 |
|
 |
2.
旧石器時代・その他の石製品
石器が出土する遺跡からは,石器を作る際にでる剥片(はくへん),石核,敲石(たたきいし)が発見されています。剥片は,製作技法によりさまざまな形をしており,縦長剥片,石刃(せきじん),翼状剥片(つばさじょうはくへん)などがあります。また、細石刃(さいせきじん)を作る際にできるスキー・スポール(スキー状削片)があります。
ここでは,栃木県磯山(いそやま)遺跡,大分県岩戸(いわと)遺跡,長野県杉久保(すぎくぼ)遺跡などから出土した石刃や翼状剥片をご覧いただけます。
左写真は,岩戸遺跡から出土した約2万年前の「こけし形」の人形です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
3.
旧石器時代・土製品
晩期旧石器時代の長崎県福井洞穴から細石刃と隆線文(りゅうせんもん)土器がいっしょに出土しています。また,新潟県田沢遺跡からは,片刃石斧と隆線文土器がいっしょに出土しています。
ここでは,これらの隆線文土器片をご覧いただけます。
左写真は,福井洞穴より出土した隆線文土器片です。(撮影:芹沢長介)
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
4.
縄文時代・土器(鉢・沼津貝塚)
土器に撚(よ)り紐(ひも)を転がした文様がついていることから縄文土器と呼ばれています。文様には,その他に爪,貝殻,竹管を使った圧痕文や押引文があります。器の形は,初期には丸底や尖底の深鉢が多く,その後,平底鉢や浅鉢も作られるようになりました。中期になると,注口(ちゅうこう)土器,台付鉢や鍔(つば)付土器なども作られています。晩期になると,さらに壺,高坏(たかつき),袖珍(しゅうちん)土器が加わるほかに,器の表面に赤色顔料で色つけしたものや黒色磨研(まけん)したものも作られました。
ここでは,縄文時代後・晩期の宮城県沼津貝塚から出土した色々な形の鉢類をご覧いただけます。
左写真は,沼津貝塚から出土した台付鉢です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
5.
縄文時代・土器(その他・沼津貝塚)
縄文時代後・晩期の宮城県沼津貝塚から出土した注口(ちゅうこう)土器,袖珍注口(しゅうちんちゅうこう)土器,壺,有孔壺,袖珍(しゅうちん)壺,有孔土器,香炉形土器,樽形土器,鳥形土器,蓋(ふた)などをご覧いただけます。
左写真は,沼津貝塚出土の壺です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
|
|
 |
6. 縄文時代・土器(その他の宮城県遺跡)
梨木畑(なしきばた)貝塚,大木囲(だいぎがこい)貝塚,糠塚(ぬかづか)貝塚,大松沢貝塚など,宮城県の縄文時代早期から晩期の貝塚から出土した土器をご覧いただけます。土器の種類としては,尖底(せんてい)深鉢,台付鉢,袖珍(しゅうちん)鉢,壺,注口(ちゅうこう)土器,甑(こしき)形土器,香炉形土器などが含まれています。
左写真は,大木囲貝塚から出土した縄文時代前期(大木6式)の深鉢です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
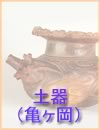 |
7. 縄文時代・土器(亀ヶ岡遺跡)
青森県木造町の亀ヶ岡遺跡は,縄文時代晩期の代表的な遺跡で国史跡に指定されています。
ここでは,亀ヶ岡遺跡から出土した鉢,深鉢,浅鉢,台付鉢,台付深鉢,壺,無頸壺(むけいつぼ),袖珍(しゅうちん)壺,注口(ちゅうこう)土器,袖珍注口土器,香炉形土器をご覧いただけます。
左写真は,亀ヶ岡遺跡出土の朱塗の注口土器です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
縄
文
時
代 |
|
 |
8. 縄文時代・土器(十腰内(とこしない)遺跡・十面沢(とづらざわ)遺跡)
青森県弘前市の縄文時代晩期の十腰内(とこしない)遺跡,十面沢(とづらざわ)遺跡から出土した土器をご覧いただけます。土器の種類は,鉢,浅鉢,台付鉢,台付浅鉢,壺,無頸壺(むけいつぼ),注口(ちゅうこう)土器,皿,片口土器,有孔土器,樽形土器,舟形土器,異形土器が含まれています。
左写真は,十腰内遺跡から出土した朱塗の注口土器です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
9. 縄文時代・土器(藤株(ふじかぶ)遺跡)
秋田県鷹巣町の縄文時代晩期の藤株遺跡から出土した土器をご覧いただけます。土器の種類としては,鉢,深鉢、浅鉢,有脚鉢,台付鉢,台付深鉢,壺,皿,注口(ちゅうこう)土器,香炉形土器が含まれています。
左写真は,藤株遺跡から出土した注口土器です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
|
|
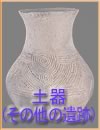 |
10. 縄文時代・土器(その他の遺跡)
主に東北地方と北海道の遺跡から出土した土器をご覧いただけます。土器の種類は,浅鉢,台付鉢,壺,皿,注口(ちゅうこう)土器,袖珍(しゅうちん)土器,有孔土器が含まれています。
左写真は,福島県会津坂下町の袋原遺跡から出土した壺です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
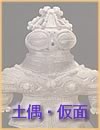 |
11. 縄文時代・土偶(どぐう),仮面
土偶は,人の形を模した土製品で,縄文時代から弥生時代に盛んに作られました。妊婦を表した土偶は,安産や繁殖を祈願して作られたと考えられています。また,一部が破損した土偶も多く出土することから呪術的な道具として使われたと想像されます。土製の仮面は,なにかの儀式に使われたと考えられています。そのほかに動物を模した土製品も作られました。
ここでは,青森県亀ヶ岡遺跡,十腰内(とこしない)遺跡,秋田県藤株(ふじかぶ)遺跡,宮城県沼津貝塚などから出土した土偶,遮光器(しゃこうき)土偶,動物土偶,土面をご覧いただけます。
左写真は,藤株遺跡から出土した遮光器土偶です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
12. 縄文時代・その他の土製品
縄文時代には,呪術的な土製品や装飾品など,さまざまなものが土で作られました。呪術的なものとして亀形土製品,土板(どばん)などがあります。また,装飾品としては,耳栓や耳飾があります。その他に漁労具の錘(おもり)も土で作られています。
ここでは,宮城県沼津(ぬまづ)貝塚,糠塚(ぬかづか)貝塚などから出土した土板や土製装身具をご覧いただけます。
左写真は,宮城県金剛寺貝塚から出土した土製耳飾です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
13. 縄文時代・骨角牙製品,貝製品(沼津貝塚、狩猟具、漁労具)
縄文時代には、固くて加工のしやすい動物の骨、角、牙を利用して釣針、銛頭、骨角鏃、根挟等の狩猟・漁労の道具類が作られました。
ここでは宮城県沼津貝塚からの出土した骨角牙製品をご覧いただけます。
左写真は宮城県沼津貝塚から出土した鹿角製の銛頭です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
14. 縄文時代・骨角牙製品,貝製品(沼津貝塚、装飾品、その他)
縄文時代には、固くて加工のしやすい動物の骨、角、牙を利用して垂飾品、ヘアピン等の装身具が作られました。
ここでは宮城県沼津貝塚から出土した装身具をご覧いただけます。
この他に、同貝塚から出土した「浮袋の口」形角製品、骨ヒをご覧いただけます。
左写真は宮城県沼津貝塚から出土した鹿角製装身具です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
15. 縄文時代・骨角牙製品,貝製品(その他の遺跡)
縄文時代には、動物の骨、角、牙や貝を利用して様々な狩猟・漁労の道具類、装飾品が作られました。
ここでは宮城県里浜貝塚、同県山畑南貝塚、同県浅部貝塚、同県幡谷貝塚、同県大木囲貝塚、同県中沢目貝塚、北海道船泊遺跡の出土品をご覧いただけます。
左写真は宮城県里浜貝塚から出土した鹿角製腰飾です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
|
|
 |
16. 縄文時代・石製品
縄文時代には,鏃(やじり)や斧のような狩猟や採取の道具のほかに,独鈷(とっこ)石や御物(ぎょぶつ)石器など呪術的なものなど,さまざまなものが石器として作られるようになりました。
ここでは,石鏃(せきぞく),石錐(いしきり),石べらなどの打製石器,石斧,擦(すり)切(きり)石斧,石皿,砥石(といし)などの道具類,石刀,青竜刀(せいりゅうとう)形石器,石棒,石冠(せっかん),独鈷石,岩偶(がんぐう),岩板などの呪術てきなものに加えて,ボタン形石製品,玉類やけつじょう耳飾などの装身具をご覧いただけます。
左写真は,青森県宇鉄(うてつ)遺跡から出土した石刀です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
|
|
 |
17. 弥生時代・土器
弥生時代の土器は回転台を使って製作され,へらや櫛を使って描かれた幾何文様によって装飾されています。東日本からは縄文や貝殻文で飾られた土器も出土しています。土器の形としては,蓋付壺,カメ,甑(こしき)や高坏(たかつき)が多く出土しています。
ここでは,青森県垂柳(たれやなぎ)遺跡,瀬野遺跡,宮城県西台畑(にしだいばた)遺跡,南小泉遺跡などからの出土品をご覧いただけます。
左写真は,宮城県円田(えんだ)遺跡から出土した長頸(ちょうけい)壺です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
弥
生
時
代 |
|
 |
18. 弥生時代・その他の土製品
弥生時代の土製品には,紡錘(ぼうすい)車,土錘(どすい)などの道具類,土偶,護符と考えられている土板(どばん)や勾玉などの装身具があります。
ここでは,青森県二枚橋遺跡から出土した土偶と土板をご覧いただけます。
左写真は,二枚橋遺跡から出土した土偶です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
19. 弥生時代・石器,石製品
弥生時代には,太形蛤刃(ふとがたはまぐりば)石斧,扁平片刃石斧,柱状(ちゅうじょう)抉入(えぐりいり)石斧,石包丁,ノミ形石器,有角石斧といった磨製石器が新たに作られるようになりました。これらの道具の一部は,木製の鍬(くわ)や鋤(すき)の加工や稲の収穫に使われたと考えられています。
ここでは,石鏃(せきぞく),石錐(いしきり),石匙(いしさじ),石箆(いしべら),石斧(いしおの),石槌(いしつち),石鍬(いしぐわ),石包丁などのほか,石偶や管玉をご覧いただけます。
左写真は,岩手県常盤(ときわ)から出土した管玉です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
|
|
 |
20. 古墳時代・土師器(はじき)
土師器は,古墳時代から平安時代にかけて製作され,日常に使われた赤褐色の素焼きの土器です。土師器は,壺,カメ,甑(こしき),高坏(たかつき),器台,坏,台付鉢,台付椀,坩(かん),小型の丸底壺など,さまざまな形態のものが作られました。土師器は,古墳時代初期には,弥生土器に形が良く似ていましたが,中期になると須恵器の影響を受けて形が変化します。
ここでは,宮城県南小泉遺跡,西台畑(にしだいはた)遺跡などから出土した土師器をご覧いただけます。
左写真は,宮城県南小泉遺跡から出土した高坏です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
|
|
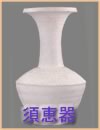 |
21. 古墳時代・須恵器(すえき)
須恵器は,古墳時代中期から平安時代まで作られた陶質の土器で,ロクロを用いて製作され,登り窯によって高温で焼成されました。須恵器は,坏,はぞう,高坏(たかつき),甑(こしき),壺,カメ,器台などのほかに,鳥形や家形をしたものも作られました。
ここでは,宮城県善応寺(ぜんのうじ)横穴群,金谷横穴群,陸奥国分寺址などから出土した須恵器をご覧いただけます。
左写真は,善応寺横穴群から出土した長頸(ちょうけい)壺です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
古
墳
時
代 |
|
 |
22. 古墳時代・埴輪(はにわ),その他の土製品
埴輪は,古墳を飾るために作られた素焼きの土製品で,円筒埴輪と形象埴輪に分けられます。形象埴輪は,人や動物,家,器財を模して作られました。
ここでは,宮城県経ノ塚古墳,台町古墳群などからの出土品をご覧いただけます。
左写真は,経ノ塚古墳出土の鎧(よろい)形埴輪[重要文化財]です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
23. 古墳時代・石製品,ガラス製品,鹿角(ろっかく)製品
古墳時代の石製品には,祭祀のために,主に滑石を素材として作られた鏡,剣,刀,玉,有孔円盤などの器物のミニチュア模造品があります。また,副葬品としてガラス製品が出土しています。
ここでは,宮城県南小泉遺跡,経ノ塚古墳などからの出土品がご覧いただけます。
左写真は,南小泉遺跡から出土した石製紡錘車(ぼうすいしゃ)です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
24. 古墳時代・金属製品
古墳時代には,鉄製武器や農耕具,青銅製の鏡などの宝器類や金銅製の装身具,
太刀飾り,馬具飾りが作られました。
ここでは,島根県植田(うえだ)横穴群などから出土した金銅製品をご覧いただけます。
左写真は,植田横穴群から出土した珠文鏡(しゅもんきょう)です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
古
代 |
|
 |
25. 古代・瓦
仏教の伝来にともなって瓦葺きの寺院や役所が建てられるようになりました。古代の瓦は,窯で焼かれた青灰色した硬い陶質のものでした。瓦は,蓮華(れんげ)の花をモチーフとした文様で飾られており,形によって軒丸瓦,軒平瓦,鬼瓦などに分けられています。
ここでは,宮城県陸奥国分寺址,菜切谷(なぎりや)廃寺址,日の出山瓦窯址群などからの出土品がご覧いただけます。
左写真は,陸奥国分寺址出土の重弁蓮華文軒丸瓦です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
江
戸
時
代 |
|
 |
26. 江戸時代・磁器類
仙台藩では,宮城県加美町切込(きりごめ)で磁器が焼かれていました。ここでは,切込西山工房址より発掘された窯道具や磁器類をご覧いただけます。
左写真は,切込西山工房址より出土した切込三彩(きりごめさんさい)の破片です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
|
|
 |
27. 北方文化資料・樺太(サハリン)(楽磨(らくま)遺跡)
樺太(サハリン)南部の時代区分は,東北日本や北海道とは異なっており,旧石器文化,新石器文化,ススヤ文化(BC800〜AD400年),オホーツク文化(AD400〜AD1200年頃)及びアイヌ文化という区分が提案されています。
ここでは,伊東信雄教授が収集したものから,樺太(サハリン)南部の西海岸にある楽磨(らくま)遺跡から出土した石器,骨器をご覧いただけます。
左写真は,楽磨遺跡から出土した石斧です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
北
方
文
化
資
料 |
|
 |
28. 北方文化資料・樺太(サハリン)(その他)
ここでは,宗仁(そうに)遺跡[新石器],ススヤ貝塚[ススヤ],幌千(ほろち)川口遺跡[ススヤ],江ノ浦貝塚[オホーツク中期],東多来加(ひがしたらいか)貝塚[オホーツク後期],南貝塚[オホーツク後期],荒栗(あらぐり)遺跡[オホーツク],来知志(らいちし)遺跡[ススヤ‐オホーツク],留多加(るたか)遺跡[オホーツク],蘭泊(らんどまり)遺跡,多蘭泊(たらんどまり)遺跡,柏浜遺跡からの出土品をご覧いただけます。
左写真は,東多来加貝塚から出土した角製銛先です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
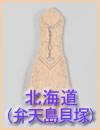 |
29. 北方文化資料・北海道(弁天島(べんてんじま)貝塚)
北海道のほかの地域では,続縄文(ぞくじょうもん)文化中期から擦文(さつもん)文化の時期に,オホーツク海沿岸地域ではオホーツク文化が発達しました。この文化では石器や金属器のほかに,海獣の骨を素材とした豊富な骨器が使われました。
ここでは,伊東信雄教授が収集したものから,弁天島貝塚[オホーツク]から収集した石器,骨製品、骨角器をご覧いただけます。
左写真は,弁天島貝塚から出土した骨牙製装飾品です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
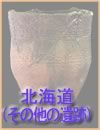 |
30. 北方文化資料・北海道(その他)
北海道の時代区分は,東北日本と異なっており,縄文時代に続いて縄文文化の要素を保持した続縄文(ぞくじょうもん)文化(AD0〜AD700頃),土器表面に木ベラでこすった跡がみられる土器によって特徴づけられる擦文(さつもん)文化(AD700頃〜AD1200頃)及びアイヌ文化に区分されています。
ここでは,手宮(てみや)[続縄文],枝幸(えさし)[擦文],サロマ湖畔,海別(うなべつ),厚別(あつべつ),枝幸(えさし)トフレユベツ,網走から収集した土器,土製品をご覧いただけます。
左写真は,手宮遺跡から出土した深鉢です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
31. 民族資料・樺太(サハリン)
これらの民族資料は伊東信雄教授が,昭和8、9年に樺太(サハリン)で収集した樺太アイヌ、オロッコの資料で,皮製品、木製品、玉製品などが含まれています。
左写真は,東タライカで収集された樺太アイヌの革製の小札(こざね)を用いた挂甲(けいこう)です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
民
族
資
料 |
|
 |
32. 民族資料・北海道
これらの民族資料は伊東信雄教授が北海道で収集したもので,皮製品、木製品、玉製品などのアイヌ民族資料が含まれています。
左写真は、アイヌのタンパクオプ(たばこ入れ)です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
33. 民族資料・台湾
この民族資料は伊東信雄教授が収集したもので、台湾の紅頭嶼(ホンタオユイ)の竹製の甲です。(撮影:東北大学考古学研究室)
|